*載積浩瀚=書籍の数が極めて多いこと。
暫らく仕事が忙しく、私邸に赴くことが出来なかった。
やっと面倒な仕事から解放され、至極の時間を味わうためにミモザの館に向かう。
車の後部座席には、今回盗んだ古書で埋まっていた。
数日をかけて本の整理し、全ての時間を読書に費やすのだ。
朝から車を運転し続け、途中買い出しやら食事をして、日の落ちる前にはミモザの館に到着した。
街から三十分程離れた静かな林の中に、まるで絵のように白い館は建っていた。
築百二十年の瀟洒な館は、その名のとおりミモザの花を満開にさせて俺を迎えてくれる。
三月初旬、色彩の乏しいこの季節に房のように咲く黄色い花が見事で、三年前にこの館を買い求めた。
終の棲家にしてもよいと考えたほど気に入った館だった。
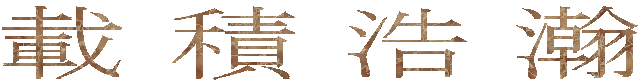 (さいせきこうかん)
(さいせきこうかん)この半年訪れることが出来ず、玄関のマホガニーの扉は重く貼り付き、ギシッと鈍い音をたてて開く。
まるで館の主が不在だったことに抗議しているかのように聞こえる。
一歩ホールに入れば外気とたいして変わらぬ室温に、ぶるりと身を震わす。
まずは長期滞在用に購入した食料と、日常生活品を車から下ろし、館全体を温めるために地下のボイラー室に種火を点けに行く。
そして奪ってきた本を抱え一階の書庫に向かえば、冷えた室内に珍客が紛れ込んでいた。
部屋の隅には本棚から抜かれた十冊近い本が散乱していた。
その横で、一冊の本を抱えた六、七歳の男の子が軽く寝息をたてて眠り込んでいる。
一体いつのまに館に忍び込んだのだ?
セキュリティ会社の怠慢に腹を立てるも、盗賊所有の館を、しかも盗んだ品を警備するというのも妙があると苦笑した。
いつからかは知らないが、男の子はここで寝起きをしていたらしく、リネン庫から毛布と枕を持ち出してきていた。
抱えていた本をゆっくりと取り上げ、近くにあった机の上に静かに置く。
そして薄汚れた小さな顔を見下ろす。
靴先で男の子のわき腹付近を軽く小突いてやれば、眠そうに上半身を起こしながら目を擦る。
「目は覚めたか?」
声に反応して、ぎょっとした顔で俺を見上げる。
「お前は何者だ?一体どこから忍び込んだ?」
腕を組み、声を低くして矢継ぎ早に質問をすれば、男の子の顔色が見る間に変わっていく。
「ご、ご免なさい、許して!お願いだから叩かないで!お巡りさんを呼ばないで!!」
身体を壁に押し付け、縋るような目付きで俺を見る。
そして目に涙を浮かべながら訴える。
叩く!?俺がそんなに暴力的な男に見えるのか。
なんて失礼なガキだ!
それにこちらとて、警察を呼ぶのは遠慮したい。
何といってもこの書庫は盗品の山なのだから。
「安心しろ、警察は呼ばないから。それに叩きもしない。だが小僧、どこから潜りこんだか言うんだ」
もう一度、同じ質問を繰りかえす。
男の子は怯えながら答えた。
小さく身軽な身体を生かして木に登り、二階の軒先にある三十センチ角の吸気ダクトから侵入したという。
侵入防止用の網はネジが緩んでおり、簡単に外せたそうだ。
まさかこんな小さな侵入者が有るとは考えてもみなかったので、無用心にも吸気ダクの管理を怠っていた。
まぁ~しょうがないと、特に盗られた物も、悪戯もしていないようなので、浮浪者のガキが寒さから逃れるために館に忍び込んだのだと、無罪放免にすることにした。
ただこのまま男の子を寒空に放り出すわけにもいかず、その処遇に思案した。
床に膝を付き、目の高さを同じにして訊ねた。
「本が好きなのか?」
男の子は緊張の色を濃くしながら、こくりと頷く。
この書庫には子供の喜びそうな本などはなかったが、図鑑を広げて楽しんでいたようだ。
先ほど机に置いた本を手に取り、無造作に開いた。
そしてそのページを見せながら質問をした。
「ここに描かれている幻獣の名前はなんと言う?」
少年は俺の顔を見て一瞬ぽかんとしたが、すぐに視線を本に戻して答えた。
「凶狸狐」
「ではその習性は?」
「変化を得意とし、飛行能力が有ります。同種は見た目に判断出来ないほどに似ていて、僅かに声が違うていど。主に家族単位で縄張りを護り、人里離なれた所で生活をしています」
「ふ~ん、ではこの幻獣は?」
次々にページを開き質問していくが、すらすらと澱みなく答えて行く。
この本は二百年前に幻獣ハンター用に作られた特別な本だ。
現存している本は十冊もなく、今では絶滅した幻獣も載っており、貴重な本だった。
従って、男の子がこの本を目にしたのはここでが始めてだろう。
それなのに、短時間で本の内容を記憶するとは。
案外と、俺は面白いモノを手に入れたのかもしれないと、ニヤリと笑う。
暫らくこのガキと生活を共にしてみるかと考えたとたん、急に気になりだした。
「それにしてもお前、臭くてたまらないな。風呂に入っていないのか?」
返事を聞かずとも分かりきっている。
今時どんな生活をしていたのかと思うほどぼろな服を身に付け、手には皸あかぎれを起こしている。
腕を捕まえ、嫌がる男の子をバスルームに引き摺って行き、暴れる身体を押さえつけて無理やり服を脱がせた。
俺は服が濡れないように上半身裸になり、ズボンの裾を捲り上げる。
その間男の子は、バスルームの隅で丸くなっていた。
なにしろこの垢に塗れた身体を洗わないことには、館に置いてやる気になれない。
まるで子供のころ、流星街で嗅いだ臭いのようだ。
丸くなった少年の腕を取り、シャワーを浴びせようと無理やり立たせれば、男の子の股間には有るべきものがなく、その時始めて女の子であることに気が付いた。
「お前、女だったのか!」
女の子は恥ずかしそうに俯き、痩せ細った身体を手で隠す。
驚きはあったものの、このままの状態にもしておけず、シャワーのカランを開き身体を洗ってやる。
スポンジで泡をたててごしごしと洗えば、一皮剥けてきれいな肌が現れたが、いたるところに紫色の痕があり、その意味に顔を歪めた。
頭は二度ばかりシャンプーすると、汚れで房のように固まっていた髪が滑らかに梳けてゆく。
そして大判のバスタオルで全身を包んで水滴を拭ってやれば、先程までの汚いガキが石鹸の香りのする可愛らしい少女へと変わる。
湯冷めをしないように新しいバスタオルに包み、暖まった寝室へと連れて行く。
そしてスツールに腰掛けさせ、濡れた髪をドライヤーで乾かしてやりながら訊ねた。
「お前の名前は何というのだ?それに歳は幾つだ?」
「名前?」
「そうだ、名前だ。まさか名前がないわけじゃないだろ?」
「名前なんてないの」
「では、今まで何と呼ばれていたんだ?」
「……七十二番」
「えっ!」
俺は少女の言葉に顔を顰めた。
ドライヤーの手を休めて話しを聞けば、親に捨てられ施設で育ち、そこでは全ての子供が番号で呼ばれていたのだと言う。
そのうえ八歳だという少女の身体は痩せ細り、同年齢の子供に比べて一周りも二周りも小さい。
劣悪な環境と、施設の人間の仕打ちに耐えかね、数日前に集団脱走をしたのだと言う。
少女は逃げるさい停まっていたトラックの荷台に隠れ、この地にやってきたのだ。
そういえば五日前、千五百キロほど離れた孤児院から集団脱走があったとニュースになっていた。
大半の子供達は即日発見され、施設に戻されたとあった。
その時の一人がこの少女なのかと、まじまじと顔を見た。
そして少女の身体に残されたアザの痕が脳裏をかすめ、思わず跪き少女を抱きしめていた。
可哀相に……ここにも自分達が過ごした子供時代と同じ世界があったのだと、心臓が締め付けられる思いだった。
力無く、抵抗出来ぬ弱き者への暴力と支配。
少女は俺に抱きつかれた意味も分からず、ただ大人しくしているだけだった。
ふと視線を上げれば窓越しに、ミモザの咲き誇る姿が飛び込んでくる。
黄色く小さな花房の塊が美しかった。
この館を購入したのも、ミモザの花が素晴らしかったからだ。
寒い冬の終わりを告げ、春の訪れを教えてくれるミモザ……
抱きしめていた腕を緩め、優しく少女の顔を覗き込んだ。
「今日からお前の名前はミモナだ」
「……ミモナ?」
「そうだ、いい名前だろ?春の走りを教えてくれるミモザの花にあやかった。もし気にいったなら、この館に住むといい」
少女の顔がぱっと明るくなり、ミモナ、ミモナと何度も嬉そうにその名を口にする。
「ありがとう、おじちゃん」
「おじちゃんではなく、俺はクロロだ。クロロ=ルシルフルだ」
おじちゃんと言われ多少のショックを覚えるが、最初が肝心と、俺のことをクロロと呼ばせることにした。
肩にかかった黒髪を梳かし、形を整えてやっていると、いきなりミモナの腹の虫が鳴く。
顔を真っ赤にして俯く姿を見て、食事をしていないのだと気が付いた。
留守がちのこの館には、水はあっても食料など保存してはいないのだ。
きっとミモナはキッチンに食料がないかと探し回ったことだろう。
「そうか、腹が減っているんだな。食材は買ってきてあるから、すぐに料理してやる」
バスタオルでは不味かろうと、何か着せようと考えるが、ミモナの身体に合った服がない。
しょうがないので俺のTシャツと、フリースのカーディガンを羽織らせたが、サイズがでかすぎ、まるでワンピースとコートを着ているかのようだった。
「明日、街に行って服を買ってやるから、今日はこれで我慢するんだ」
ミモナは嬉しそうに微笑んだ。
そして荒れた手と足に薬を塗り、食堂へと連れて行く。
俺の大して美味くもない手料理を、がつがつと犬のように喰う。
その勢いは、皿までも喰うのではないかという勢いだった。
よっぽど飢えていたのだろう。
その喰らうさまが俺の子供のころのようで、可笑しくもあり切なくもあった。
まぁいいさ。徐々にマナーを教え、レディになるべき教育をしていけばいいのだ。
ミモナは賢かった。
俺の与える知識を、乾いた砂漠が水を吸うかのごとく吸収して行く。
一日の大半を書庫で共に過ごす。
ソファーとテーブルを持ち込み、ミモナの勉強を見てやる。
一生懸命に勉強した御褒美に、ミモナの望んだ本の読み聞かせをするのが日課になっていた。
ソファーに腰掛ける俺の膝に座り、じっと本の内容に耳を傾ける。
時折りこちらを驚かすような質問をしてくるが、彼女が理解できるまで何度も説明してやった。
そんな時間が俺にとっては楽しく、幻影旅団の団長ともあろう者が何をしているのかと、その度に苦笑した。
だが落ち着いた生活もそうは長く続かず、仕事と称して館を空けることが多くなってくる。
ミモナは何かを感じているらしく、仕事について訊ねてくることはなかったが、出かけるたびに寂しげな顔で俺を見送った。
俺もまた、盗賊家業について触れることはしなかったが、俺の闇の部分に薄々気が付いていることに心を痛めた。
そんな中、彼女に仕事として与えたが書庫の管理だった。
小さな管理人は俺の留守の間に本を整理し、俺より本の在りかに詳しくなっていった。
ミモナが留守中の寂しさを、本の整理で紛らわしていることには気が付いていた。
帰宅のさいは、ミモナの好みそうな本をお土産にする。
抱きついて喜ぶ姿に、俺は幸せを感じた。
ミモナといる時間が平和で、ただのクロロ=ルシルフルを曝け出される時間でもあった。
増える書庫の本と同じように、俺とミモナは信頼と愛情を積み上げていった。
あれから九年、ミモナも十七歳になっていた。
彼女を女好きの男団員のターゲットにならぬよう、ホームに連れていくことなく、ミモザの館で極秘裏に育てた。
教育した人間が好かったのか才色兼備に育ち、街を歩けば男共の視線を釘付けにする。
外出する時は善からぬ虫が付かぬよう、俺の腕に細く長い彼女の腕を絡めさせ、しっかりとガードする。
アイジエン大陸系独特の黒曜石の瞳も、漆黒のロングヘアーも、華奢でありながら出るところは出た身体も、俺を満足させるには十分だった。
特に黒い瞳を飾る長い睫毛に、赤みを帯びたふっくらとした唇が何ともいえない。
館では俺の膝に座り、本を読むのが子供の頃からの習慣になっている。
出合った時よりはかなり重くなったが、薄くごつごつしていた小さな尻から、丸みを帯びた柔らかい尻へと変わり、腿にあたる感触も好くなっていた。
女性的になった腰に腕を廻し、ミモナに話しかける。
「何か読みたい本はあるのか?」
「う~ん、たくさんあるけど……」
「遠慮しなくていいんだ、何でも盗ってきてやるから。どうせ俺も欲しい古書があるから、一緒に手に入れてやる」
と言ってみたものの、いつだってミモナは欲しいものがあっても遠慮がちだ。
すでに彼女には、俺が盗賊の頭であることは話してあった。
大きくなったミモナに俺の仕事が何であるか、誤魔化すのには無理があったからだ。
ミモナが重い口を開く。
「クロロが一度仕事に出かけたら、最低でも一週間は帰ってこないでしょ。私、帰ってくるまで心配で、もしもクロロの身に何かあったらどうしよう。だったら何もいらないから、いつも側にいて欲しいの」
ミモナのあまりの心配ぶりに、胸を突かれるような思いがした。
「大丈夫さ、大切なミモナを置いて先に逝くようなことは無いから」
「絶対に、絶対に約束よ!」
不安気に顔をくもらせるミモナの額に口付ける。
親に捨てられたミモナにとって、俺は唯一の家族であった。
父親であり、兄であり、時として母親でもあった。
俺を男として見ることはなく、常に保護者を見る目だった。
だから今でも俺の膝に座り、甘えてくるのだ。
そして書庫は、ミモナにとって母親の子宮のようなものだった。
落ち着き、安らぎ、知恵と知識という栄養を与えてくれる。
得られぬミモナ……
一緒にいることが、今の俺に出来る愛情表現でしかない。
だがそれでもいいのだと、今は思うことにした。
二人で書庫にいる時間が最高の幸せなのだと。
いつかこの場所で、愛を紡げるようになると……信じてお前を待ち続ける。
なぜならば、俺は一番教えたいことを、まだお前には教えていないのだから……
End
2017/08/17 改稿
2009/03/19 加筆・修正
2007/08/19
ある種、育成ゲーム的な物語……