*空空寂寂=無心なさま。無関心、無反応であったり、ひっそりと寂しい様子。
彼はストレートの長い黒髪を、バルコニーから吹き込んでくる風に靡かせる
長身で細身の身体は、身軽で切れが有りそうだった
右手の指には鋲のようなものを数本挟む
整った顔は無表情で、黒い大きな瞳で私を見ている
彼女の美しい漆黒の髪は腰にまでとどく
華奢な体格だが四肢がすっと伸び、女としては背は高い
美しい顔立ちだが、感情の起伏が見えてこない
黒曜石のように冷えきった瞳が、オレを静かに見つめていた
まるで鏡を見ているような二人の出会い……
そして、すべてがモノトーンの世界で始まった
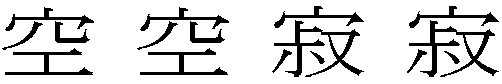 (くうくうじゃくじゃく)
(くうくうじゃくじゃく)オレと彼女の間には、オレがたった今殺した男が転がっていた。
男の名前はジョン=バレンタイン、年は五十七歳。
職業は……何だったかな?
親父からこの男の説明は一通り聞いてはいたが、暗殺には直接関係ないので、たいして憶える気もなかった。
と言うよりは、殺す相手に興味を持ってもしょうがない。
オレは暗殺者として依頼された仕事を全うするだけ。
殺す理由があるのは依頼者で、俺に理由は必要なかった。
暗殺も滞りなく完了し、親父にゾルディック家専用無線機で連絡をしたところで、彼女が部屋に入ってきた。
気配がなく、いつのまにかオレの視界に紛れ込んでいたと言うべきか。
子供の頃から暗殺者として育てられたオレに、僅かばかりの気配を悟られることなく、そこに立っていた。
その細い腕には、水差しと錠剤が乗せられた銀の小さなトレイ。
オレ達は否応なく正面から向き合ってしまう。
すでに彼女が部屋に現れてから五分は経っているだろうか。
別の言い方をすれば、ターゲットを処分してから六分が経過していた。
暗殺の基本は、仕事が完了した時点ですぐにその場を離れること。
その原則を無視し、オレはこの場に留まっている。
まるで床に縫い付けられてしまったように動けず、彼女を凝視する。
互いの間の空気が圧縮されるようだ。
いつまで続くか分らない沈黙の中、耐えきれずに先に口を開いたのは、意外にもオレだった。
「君、疲れるだろ?そのトレイをテーブルに置いたらどう」
均衡を破るにしては、何とも間抜けな会話で始まった。
彼女はオレが勧めたとおり、無言ですぐ横にあったテーブルにトレイを置いた。
取り敢えず、耳は聞こえているらしい。
そして再び彼女は俺を見つめていたが、その姿は部屋の情景に溶けてしまいそうなくらい存在感が薄い。
彼女には、オレ達の足元に倒れている男が見えていないのだろうか?
それとも倒れている男が寝ているとでも思っているのか?
そんなはずはない……出血こそしてはいないが、俺が投げた鋲が三本も深々と顔面に刺さっているのだから。
目を見開き倒れている男が、すでに死んでいることは十分承知しているはず。
なのに彼女は顔色も変えなければ、悲鳴の一つもあげない。
「君……怖くないの?そこに倒れている男を殺したのはオレなんだけど」
暗殺者が暗殺したことを語ってどうする。
再び大間抜けなことを言ってしまったことを後悔をしていると、彼女の口がゆっくりと開く。
「お父様を殺して下さって有り難う」
予想もしていなかった返事に俺は驚いた。
お父様?その響きに妙なものを感じながら、なぜ父親を殺されているのに礼を言われるのかと不思議に思う。
すると彼女はオレの考えを読んだかのように、無表情に言った。
「お父様とは血が繋がっていないの。私はお母様の連れ子だから」
床に伏した男と彼女を見比べた。
お義父様……美しいが印象の薄い彼女に対し父親は、小柄で貧弱、顔は欲のために醜く歪んでいた。
どこをどう取っても、彼女の言うとおり血の繋がりがあるとは思えない。
視線を元に戻せば、彼女の口元に仄かな笑みが浮かぶ。
「あなたがお父様を殺してくれなくても、いずれこの男は死んだの。私が少しずつ、毒を飲ませていたから」
彼女は毎日持病を持つ父親の薬の中に、少しずつ毒を混ぜていたと話す。
そんなこと、見ず知らずのオレに語っていいのか……
名ばかりの貧しい貴族の娘に生まれた母親は、美貌を武器に裕福な男と理想的な結婚をするが、数年で夫は亡くなる。
相続する遺産は蓋を開ければ借金という名前のものばかり。
母親は相続を放棄し、幼い娘を連れて実家に戻る。
当然のごとく祖父母に母娘を養う力は無く、娘の次の嫁ぎ先を探す。
見合いをした金貸しの男はえらく女を気に入り、すぐに結婚を申し込んできた。
女は男を好まなかったが、娘もおり贅沢の言える状態ではなく、その申し込みをしかたなく受ける。
優しかったはずの男が結婚をきっかけに、母親に暴力を振るうようになる。
毎日振るわれる暴力の嵐に、母親の精神が少しずつ崩壊してゆく。
没落貴族の女にとって美しさだけが武器であったが、男から逃げて娘を養うだけの勇気はなかった。
母娘は金銭的に満ち足りた生活を保障された代わりに、籠の鳥となる。
鳥というよりは、生きた玩具だったのかもしれない。
娘である彼女は子供の頃からそんな母親を見続けていた。
館の中では何も見ず、息を殺し自分の存在を消す。
そうでもしなければ、見たくないものを見てしまうことになる。
彼女の存在は空気のようなもの。
だが最近になって母親が自らの命を断った。
すると暴力の矛先が自分に向けられ、義父に性的虐待を受けた。
館を逃げ出したかったが、いつも使用人に見張られ叶わぬ夢。
母への想い、自由への想いが憎しみから殺意へと変わるのに時間はかからない。
籠から逃げられないなら、男を殺せばいい。
そして持病を持つ男の薬に、少しずつ毒を混ぜていった。
やせ細った男は車椅子の生活となり、言葉を話すことも難しくなる。
必然的に彼女は暴力を振るわれることはなくなったが、毒は盛り続けられた。
淡々と続けれた彼女の話し……
彼女の理由など、オレにはどうでもよかった。
問題は、暗殺者のオレの顔を見たということ。
親父からは金にならない殺しはするなと言われていたが、顔を見られたら殺せとも言われていた。
それなのに、なぜオレは最後まで彼女の話しを聞いていたのか……
「悪いけど死んでくれるかな?君はオレの顔を見てしまったから」
ボソリと言った言葉……
悪いけど?オレは何を謝っているのだろう。
これから殺す奴に、わざわざ謝ってどうするのだ。
彼女は命ごいも逃げもせず、その場に臆することなく立っていた。
オレは一歩二歩と彼女に近づき、彼女の動かぬ義父を跨いだ。
その瞬間、彼女の黒曜石の瞳が涙で潤み、一滴の滴が頬を伝わる。
そして冷え切った瞳は体温を取り戻したように、生気を帯びて輝きだす。
「本当に……本当に、あの男は死んだのね」
俺は首を縦に振り、鋲を挟む指を高くかざした。
モノトーンだった世界が急激に色を取り戻して行く。
華が咲いたように鮮やかに色を増す中で、彼女は微動だもせずに微笑む。
その唇から漏れた言葉は、
「あ り が と う あ な た」
刹那……
オレは上げた腕を、彼女の額を目掛けて振り下ろす。
鋲は狙いを外すことなく深々と彼女の額を貫く。
薄い皮膚を突き破り、八ミリほどある厚い前頭骨も突き抜け、脳に達する。
黒曜石の瞳を見開き、仰け反るように後ろへ倒れてゆく彼女の細い腰を抱きかかえ、全体重を片腕で支える。
がっくりと崩れ落ちた彼女の顔に優しく触れ、その目を閉じてやる。
木漏れ日の中を二人で散歩する。
「イルミ、イルミ、大好きよ」
何の遠慮もなく口付けを求め、甘えてくるゼフィルス。
その太陽のような笑顔に誘われ、顎を取る。
「オレもだよ、ゼフィルス」
まるで昔から知っている関係のように当たり前に言うが、ゼフィルスには記憶が無かった。
そう、あの日を境にして……
彼女の額には、深く針を刺し込んである。
殺さねばならぬ彼女を連れ帰り、親父には渋い顔をされてしまったが、記憶を消すことを条件に、ゾルディック家に置くことを許可してくれた。
仮死状態にしてあった彼女の額から鋲を抜き取り、替わりに細くて長い針を刺す。
目覚めた彼女はオレの顔だけを覚えていた。
彼女が二度と空空寂寂とした思いをせず、その華のような笑顔を失うことがないようにと、深くゼフィルスに口付ける。
End
2017/05/17 改稿
2009/03/19 加筆・修正
2007/09/10