幻影旅団 12
女どものいないホームでの酒宴は盛り上がる。
車座になり、バカ話しのオンパレード。
もちろん話しの内容は色事が多く、尾鰭を付けて面白可笑しく話される。
飲み進む酒の量に比例して、話しの内容はより過激になって行く。
べろんべろんに酔ったウボォーギンが、顔を真っ赤にして酒臭い息を撒き散らし、カミングアウトしたから堪らない。。。
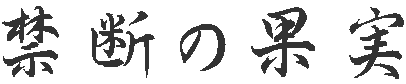
「聞いて驚くな!今だから話すが、オレはケイに一時惚れていた。片想いだが、出来ればアイツと一発やりたかったぜ!」
ウボォーギンが何を言い出すのかと、飲む手を休め真剣に聞き入った男達の顔に爆笑はなく、困惑の色が浮かぶ。
「……ケイ?ケイって、あのケイか?」(フィンクス)
「……そういえば、そんな名前の奴がいたな」(フランクリン)
「確かにいたあるね。今フィンクスが言わなければ、永遠に思い出さなかった名前ね」(フェイタン)
「言われてみればそうだな。あの頃はメンバーの入れ替わりが激しかったから、名前を忘れていてもしょうがないが」(シャルナーク)
「ケイか……そういえばあいつ、いつの間にかいなくなったな」(ノブナガ)
ウボォーギンが呼び水をしなければ、誰からも忘れられていた名前。
またウボォーギン自身、酒の量が超えていたために、仲間のエロ話しで記憶のどこかが刺激を受け、偶然で思い出した名前だった。
シャルナークの言うメンバーの入れ替わりとは、新たに加わった仲間の幼い死を意味する。
大抵の場合、流星街でも最悪と言われる彼らの育った土地では、食料不足による病で体力のない小さな子から淘汰されて行く。
他にも不慮の事故や、他グループとの抗争で命を失う場合もある。
そのせいで、名前を覚える前に逝なくなってしまうこともあるほどだ。
その中でケイの名前は少し特別だったようで、男達はちくりとしたものを感じながら反応する。
互いに顔を見合わせ、その名前を確認し合う。
「確かにいたな……細面の女のような顔をした奴だった」(フィンクス)
「そうだったか?確かに可愛い顔はしていたが、割と男っぽかったと思うが」(フランクリン)
「いやっ、違うあるね。鋭さのある、キツイ顔ね。でも、時として愛くるしい表情をするある」(フェイタン)
「それも違うだろ。凛々しいというか、スッキリとした顔立ちだったと思うが。痩せてはいたが背は高く、いい男だった」(ノブナガ)
「そうかな……俺は特徴のない顔だったと思うけど……背も低からず高からず。でも、なんとなく可愛いかった印象はあるけど」(シャルナーク)
ケイに対する雰囲気の印象は様々だったとしても、外見が大きく食い違うことに男達は違和感を覚える。
そこで一人だまる男に視線が注がれる。
何も言わぬ男は顎に手をやり、俯き気味に何かを考えていた。
そして何かの結論を得たかのように面を上げる。
そして男は一発の爆弾を投下した。
「ケイは襟元まである黒髪の少年だったよな?」
男の発言に、その場の空気が凍る。
酔いの回っていたはずのウボォーギンが、まるでしらふのようにはっきりとした口調で言った。
「いや、違うだろ。あいつは赤髪だった」(ウボォーギン)
ウボォーギンを皮切りに、次々とケイの髪の色が飛び出す。
「違うよ、ウボォー。ケイの髪の色はブロンドだ。俺の大好きなブロンドだから、絶対に記憶違いはないよ」(シャルナーク)
「ならば言わせてもらうが、ケイの髪色は栗色だ。俺も好きな髪の色だから、絶対に間違えていないぞ!」(フィンクス)
「オレは団長の意見に賛成だな。俺の記憶する限り、ケイの髪の色は黒だ!」(ノブナガ)
「いやいや、お前達の記憶はいい加減だな。ケイの髪色は亜麻色だったはず」(フランクリン)
「みんな適当な記憶ね。ワタシが結論を出すあるね。ケイの髪色は///」(フェイタン)
小柄な男の意見を遮り、額に刺青のある男が衝撃的な言葉を口にする。
「フェイタンは、ケイの髪色は茶褐色だったと言いたいんだろ?」
フェイタンと呼ばれた小柄な男は、言い当てられたことに驚きの色を目に浮かべた。
他の男達も尋常ではない表情をするが、刺青のある男だけはニヤリとしながら冷静に言った。
「シャルナークとフィンクスが言う好きな色は、好みの女の髪色の話しだ。つまり俺達が今話しているケイの髪色は、自分達の好みの女の髪色を無意識に言っているに過ぎない。つまり俺達が話していたケイの印象や姿形は、俺達の性的好みを反映させているということだ」
「だから……だから、団長は何が言いたいんだ」(ノブナガ)
団長と呼ばれた刺青のある男は話しを続ける。
「……まずケイのフルネームだが、あいつはケイ=アボリニックと名乗っていた。ただし今となってはそれが本名かどうかは不明だ。そして俺がケイに持つ印象は、大人しく、男に言うのも何だが、清爽な感じのする美少年。そして皆が言うように、可愛らしさのある少年だった」
「だから、それで!?」(ノブナガ)
急ぎせかす髪の長い男同様に、男達の表情には好奇心がありありと浮かぶ。
「まずケイと呼ばれた人物は本当に存在したのか?名前はどうあれ、その人物は存在したと考えるべきだろう」
「……考えるべきとはどういうことだ。だいたいケイは団長が拾ってきたガキだろう?それが存在したかしないかの論議になるとはどういうことなんだ」(フランクリン)
「あいにくだが、ケイは俺が拾ってきた子供じゃない」
互いに顔を見合わせる男達は謎解きのような話しに、自分達の記憶に懐疑を感じ始める。
「ならばなぜ?いつからオレ達のグループにケイはいたんだろう?」(シャルナーク)
気が付けば、ケイはいつの間にか俺達のグループに当たり前のように存在していた。
だいたいの場合、ゴミ捨て場に捨てられた子供を拾ってくるのはクロロだった。
ただし拾ってくるといっても、クロロのお眼鏡に叶った子供だけで、むやみやたらに拾ってくるわけではない。
あくまでもグループに馴染みそうな性格で、なおかつ体力がありそうな者を選別する。
もしくは何らかの秀でた能力を持っていそうな者。
残酷な選択肢だったが、心身に病があれば他の仲間に負担と危険にさらす可能性もあり、グループの存続に影響する。
また一つのグループが養っていける人数の許容範囲が狭いこともある。
本来は思いやりのあるクロロにとって、命の選別は断腸の思いだったはず。
だがケイはクロロが拾ってきたわけではなく、いつのまにかオレ達のグループに紛れ込んでいたのだ。
そのことに気が付いていた者はクロロくらいだが、それもあやふやなものらしい。
クロロですらそれなのだから、オレ達にいつからと言われても、具体的な日付を言える者などいるはずがない。
だがケイは間違いなく存在したのだ。
「……俺の考えることはこうだ」
オレ達はクロロの言葉を待った。
「ケイにとって、俺達のグループに紛れ込むことで何のメリットがある?この流星街にとって生きることの最大の目的は食料を得ることだ。実際のところ、あいつは間違いなく皆より少ない食料を多く得た」
クロロはそう言いながら、そこにいる全員の顔を見回す。
するとオレを含め、皆気まずそうな顔をした。
「……気にするな。俺だって、ケイに自分の食料を分け与えた一人なのだから。そしてあいつが、お前達からも陰で食料を分けて貰っているのは薄々知っていた。だから逆を言えば、あいつの存在に気が付いたんだ。否、あいつの存在に関心を持ったんだ」
「確かにクロロの言うとおりだ。オレもケイに僅かだが、時たま食料を分け与えていた」(フィンクス)
オレが思わずそう口にすると、オレもオレもと声があがる。
「要するにケイは、皆で平等に分けた食料以外に、さらに少しずつの食料を皆から貰っていたわけだ。つまり、誰よりも多くの食料を得たということか」(フランクリン)
「……どうやらそういうことになりそうだな。一人の者から多く得るより、多くの者から少しずつ得た方が確実で効率がいい。それがケイの狙いだろ。そのために、自分に好意を持たせるように仕向けたということだ」
「ケイが何者であるかは分からない。ただ一つ言えることは、あいつが何らかの方法で、自分の姿を相手の好みに見せる能力があったということだ。たぶん視覚と言うより、脳に直接働きかけていたんだと推測する」
「つまりケイは念能力者だったということか?」(フランクリン)
「……たぶん」
「ならば俺同様に、操作系能力者だったってこと?」(シャルナーク)
「否、そうとも言えない。なぜならあいつが操作のためにアンテナを刺したとは考えづらい。むしろ特質系なんじゃないかと思う。しかも鍛錬することによって目覚めた能力ではなく、生まれつき持ち合わせていたとか、環境に合わせて自然に目覚めたとかの類だと考える」(クロロ)
オレ達は予想だにしなかった話しの展開に、クロロの話しに聞き入った。
「ケイは相手に好意を持たせることで、自分に対する利益を生み出す。そために相手好みのイメージを作り出す。男なんて単純なものだが、実に的を得ている。しかも同性が相手となると、好意をダイレクトに表すのはけっこう難しいものだ。周りの目も憚られるし、その趣味がなければ多少の罪悪感も生まれる。そこがヤツの狙い目でもあるのだろう。親密な関係にはならず、それでいて相手から好意という物を得られる程度の距離感が大事なんだ」
すると怪訝な顔でシャルナークが言った。
「ならば俺達のグループではなく、もっと力の強い大人の連中に取り入れば、もっと美味しい思いが出来ただろうに」(シャルナーク)
「それは考え方にもよるな。確かに相手が力のある大人であれば、もっと美味しい思いが出来たかもしれないが、間違いなくそいつらの食い物にされるだろうな」
皆の顔がはっとした。
確かに大人なら、ほのかな好意では済まなくなるだろう。
もっと肉欲的で、従属的な関係を強いられる可能性が高い。
子供相手ならその可能性も低く、上手くかわせる可能性が大きい。
事実、俺達の中にケイに手を出したヤツはいない。
ウボォーですら一発やりたかったと言葉では言うものの、ヤツの身体には指一本触れてはいない。
一瞬沈黙が生まれた中で、今度はクロロがカミングアウトした。
「俺はケイに手を出した。出したと言ってもキスをしただけだかな」
その場にいた全員がクロロを凝視する。
「……そんな目で見るな。まるでアイドルに手を出した犯罪者を見るような目付きだな。俺はあいつの正体を確認したかっただけなんだ。俺が引き入れた子供ではないと分かっていながら、一方でヤツの存在を当たり前のように認めている矛盾。しかも好意という名のもとにおいて、おかしいと思うだろ」
クロロが苦笑しながら言えば、フェイタンが鋭く突っ込む。
「それでケイは団長がキスした時、どんな反応を示したあるか?」(フェイタン)
そう思っても訊きづらい質問を、フェイタンが間髪を入れずに訊いてくれた。
「そうだな……最初は驚いていたが、嫌ではなかったと思う。その証拠に、俺の差し入れた舌を受け入れていたからな」
団長!そりゃあ、完全にカミングアウトだぜ!!
オレ達が唖然としていると、クロロの話しは淡々と続く。
「……だからケイは、俺達のグループからいなくなったんだと思う。もしかするとあいつにあんな風に触れた男は、俺が初めてだったのかもしれない。それまでは間一髪で交わしていたんじゃないかな。身に危険を感じれば、次のグループに移動する。奴はそんなことを繰り返していたんだと思う。浅く広く……それがあいつの生きる術なんだろうな。深く狭く付き合えば、しがらみや腐れ縁に飲み込まれてしまうから」
たぶんクロロでなくても、時間が経てばいずれかは誰かがケイに手を出していたのかもしれない。
クロロが言うように、ケイはアイドル的存在だったのだ。
触れてはいけない禁断の果実。
クロロに触れられたことによって偶像は傾向しかねない。
ヤツはそのことを恐れたのだろう。
実のところ、ケイにもクロロに対し多少の好意はあったのだと思う。
だからキスを拒まなかった……
「それでケイは、今どうしているのかな?クロロが言うように、今もどこかのグループや組織に紛れ込んでいるのかもしれないね」(シャルナーク)
「……ケイは静かに暮らしたかったのだと思う。ただ力もなく、誰かに依存しないと生きてはいけなかった。だから相手の好きなタイプに擬態していたのだろう。だから目立たぬよう、いなくなる時も人の意識に残らないようにいなくなった」
ウボォーが言わなければ忘れていた禁断の名前。
決して熟れることのない果実。
不思議な果実に触れてしまえば、儚くも泡のごとく消えてしまう……
その後オレ達はケイの話しをやめ、相変わらずのバカ話しに始終した。
End
2017/06/09
![]() Back
Back
随分長いこと、バックヤードに書きかけで放置していた。やっと日の目が……眩しい✨