皮肉を言うのが上手かった
言葉尻をとらえるのも絶妙だった
あら捜しをしているわけではないのだろうが、何かと俺に感応してくる
俺に関心を持っているからこその反応
涼しい顔を装い、子供のころから一言一言に共鳴していた
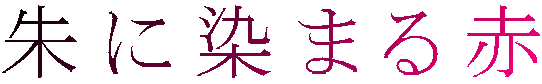
子供の頃から俺の後を一途についてきた。
服の裾を小さな手で握り離そうとはしない。
俺との数歳の差が歩幅に表れ、俺が少しでも急ぎ足になると引きずられて歩くことになってしまう。
そのために躓いたり息を乱したりするので、その度に俺は慌てて立ち止まる。
そして手を繋いでゆっくりと歩いてやれば、嬉しそうに俺を見上げる。
まるで鳥の雛の刷り込み行動を見ているようだった。
やっと目の開あいた雛が、初めて見た自分より大きな動くモノを母親だと認識する行動に似ていた。
動くモノであれば何でもよかったのか・・・それとも自分を愛してくれる者であればよかったのか・・・
幸か不幸か、雛は俺のことを親として選んでしまったようだ。
親に選ばれた方も利発で可愛い顔に見上げられれば嬉しく、時には大きな翠の目をうるうるさせるものだから、思わず抱きしめずにはいられなかった。
もっともゴミ捨て場から廃棄された雛を見付け、持ち帰ってしまったのは俺だから、面倒をみる責任は必然的にあった。
最初はピーピーと鳴いて、ともかく一人でいることを怖がった。
夜でなくても暗いところを恐れ、がたがたと震える。
だから夜は一緒の毛布にくるまり抱いて寝た。
すると安心しきってすやすやとよく眠る。
絵画にある天使のような寝顔に、罪がないものだと苦笑いをしてしまう。
おかげでよく懐き、言うこともよくきいた。
何でも俺の真似をしたがり、どこへ行くにも付いてくる。
鬱陶しいとか邪魔に感じたことはなかったが、『何故?』『どうして?』と訊かれると困ってしまう。
雛は賢い子で、何でも理解したうえでなければ納得しない。
当時は俺も子供で知らないことが多く、本で学んだ座学の知識と身近な経験で得た術を雛に教えることで精一杯。
それでもだんだんと知識以外に知恵というものを学び始める。
その中で、世を上手く渡るための処世術なるものも身に付けてゆく。
柔軟な脳は良いことも悪いことも素直に吸収していった。
だから大人になっていく中で俺が女達と付き合うようになると、その親密なる時間に気を配らざる得なくなってくる。
雛が寝付いたのを見計らい、息を潜めてそっと寝床を抜け出し女の許へ行く。
一時の快楽を貪り、朝がやってくる前にホームへと戻る。
足音を忍ばせ寝床に潜り込むが、寝ているはずの雛が目に涙を溜め『どこに行ってたの?』と、切ない声で訊いてくる。
どこに行って何をやっていたかなんて薄々気が付いているくせに、一人にされたことへの抗議を籠めて訊いてきた。
ともかく一人で夜を過ごすのを怖がる奴で、よほどのトラウマがあるのだろう。
だがそのことについて訊ねることはしなかった。
話したければ自分から話すだろうし、嫌なら話さないだけのこと。
もしかしたら原因などはとうに忘れてしまい、闇夜に対する恐怖だけが残っているのもかもしれない。
だが抗議をされたところで俺にもプライベートな時間が必要で、健康な男子として生理的な欲求も大きかった。
そこは雛の立ち入ることの出来ない領域で、『お前はまだ子供だから』と諭すしかなかった。
そのことを元より知っていて、文句を言いたくても言えないことにやる瀬ない顔で俺を批判する。
まだお前には早すぎる・・・時が経てばどこにでも連れて行ってやるから。
そして自分の翼で好きなように飛べばいい。
久しぶりにホームに帰ってきた。
ホームに誰が居るかなんて気にしたことはないが、ここをベースにしているフランクリンとマチを含め、常に入れ替わりで三、四人のメンバーがいることが多い。
だがその日に限っては、俺同様に久々に戻ってきたシャルナークと俺の懐かしい我が家となった。
子供のころから無計画に廃材で建て増しをしてきたホームは歪な形をしていたが、それなりの広さはある。
最盛期はこの空間に、二十人前後の子供達が共同生活をしていた。
ホームの中を駆け回る足音に、些細なことで喧嘩する声。
それに厳しい日々の暮らしの中でも絶えなかった笑い声・・・
だが全ての雛が上手く巣立つわけじゃない。
過酷な環境の中で大半は自然淘汰されてしまう。
おかげで二人しかいない空間がとても広く感じられ、話し声がホーム全体に響いているような気がする。
考えてみればこのホームとは十五年以上の付き合いだが、たった二人だけというのは初めてかもしれない。
思い出に浸るわけではないが、サロンのソファーに座り吹き抜けの天井を見上げてしまう。
ウボォーの二階を作ろうぜの一言で、寝床になっていたこの空間がサロンとなって階段が取り付けられた。
最初のころは階段といっても梯子で、出来上がった二階へ垂直に上り下りをしていた。
じきにそれでは使い辛いと、パクとマチから苦情が出て今の階段が取り付けられる。
それにここがまだ掘っ立て小屋だったころ、このソファーのあたりで俺はシャルナークを抱いて寝ていた。
腕の中にすっぽり納まっていた雛が、今や忠実ではあるが小生意気な若造に育った。
身体だって俺よりでかくなっている。
見上げた吹き抜けに時の流れを感じてしまう。
「クロロ、淹れたよ」
シャルナークがソファーに座る俺の目の前に、湯気の立つマグカップをスッと差し出してくる。
鼻腔を刺激する香り高いコーヒー・・・
好みを知り尽くした淹れ方に安心感を覚えてしまう。
どんなに深く付き合った女でも、こうは淹れられない。
熱いコーヒーを口にすれば思わず笑みが漏れ、それを見ているシャルナークの顔にも笑みが浮かぶ。
「珍しいね。クロロがホームにやってくるなんて」
「そういうお前だってホームにはほとんど寄り付かないだろ」
「だって、ここに来る理由がないからね。今回はたまたま用事があって戻って来ただけだよ。ホームに居着いているのはマチとフランクリンぐらい。二人のおかげでホームは維持されているから感謝しているけれど、何でこんなところに執着しているのか分からない」
「そうだな。あいつらにはあいつらの理由があってここに留まっているのだからな」
「俺だってホームをわざと避けているわけじゃないけど、生活のベースが外に移ってしまったから、ここにやって来る回数が減っただけのこと」
そう言いながら俺の右隣に腰を下ろす。
「生活のベースって、ようは女のところだろ?」
いつもなら言葉尻を取らえるのはシャルナークだったが、今日は俺が先に取っていた。
一度巣立ちした若鳥は、二度とその巣には戻らないというが・・・
若鶏は親鳥と別れたかったわけじゃない。
常に目の前を行く親の背を見て、同じ生き方をしたいと願っていた。
だから親鳥のやること成すことを真似してきた。
知識も知恵も遅れをとるまいと猛烈に本を読み、学識を必死に広げてゆく。
その姿がまるで俺のようだとノブナガが笑った。
少し早かったが、シャルナークを連れて女を買いに行った。
それをきっかけに徐々に奴とは距離をおいていくが、寂しさを紛らわすためか女のところに入り浸り、ホームに帰ってこない夜が多くなる。
一夜の恋に快楽を求め、受け入れた女の胸で安堵して眠る。
そのくせ目覚めれば冷たいものだったらしく、引き止める女を突き放してホームに戻り、何事も無かったかのように日々を送る。
またグループ内の女との色恋沙汰には見向きもせず、告白をした女が居た堪れなくなってホームを出ていってしまうことが幾度かあった。
見かねて一言言うと、『クロロだって同じでしょ。グループ内でやっかいなことには巻き込まれたくないからね』と、皮肉とも嫌味とも取れることを口にした。注1
「そう女のところだよ。自分の部屋に女を入れるのは気がすすまない。だからやる時は女の家に行くか、ホテルを利用さ。たまに車の中の時もあるけどね」
悪びれもせず、当然のように言う。
それは俺を見習っているからとでも言いたげだった。
子は親の背を見て育つというが、他人同士だったら何というのだろう?
朱に染まろうとする赤とでも言うのか?
だが朱もまた赤に染まっていったことに気が付かない。
注1:『ささやかな抵抗』『ささやかな抵抗 side:クロロ』『spider』地下格納庫参照
End
2017/02/23 改稿
2009/06/12
巣立ちを促すクロロ。子離れしているようでしていないクロロか・・・