月明かりに照らされた石は、昼間の太陽光の下で見るよりも魅惑的に見えるから不思議だ。
神秘性がより高まり、我が手に収めたという満足よりも、羽が生えて逃げて行くのではないかという不安。
その証拠に今し方、とある宝石商の自宅から奪った宝石を指に挟み、月明かりに翳していた。
すると満月から降り注ぐ青白い光りが巨大なサファイアに吸い込まれ、感じるはずのない光りの質量を指先に感じてしまう。
その独特で玄妙な輝きに見入られ、しばし時が経つのも忘れていた。
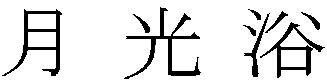
どこまでも続く枯れた臙脂色の甍の上に立っていた
視界を遮るものはなく、限りなく月との距離が近い
初夏だというのに冷めた月光は、俺の影を波打つ甍に映し出す
「…おい、団長!」
野太い声が甍の波によく通る。
全神経が指先にある宝石に集中しているさなか、聴覚だけが現実に引き戻される。
「何だ、フィンクス。もう少し楽しませろよ」
エクスタシーにも近い陶酔感を邪魔され、不平が喉からこみ上げて来る。
「その石が気に入っているのは分かるが、何もここで鑑賞に耽らなくても、ホームに戻ってから十分に堪能すればいいだろ。目的のブツはいただいたんだ。さっさと引き上げようぜ」
実に事務的で模範的な忠告。
仕事をやり終えた場所に、長居は無用だということは理解している。
そろそろ襲った宝石商の館に入っている警備会社が騒ぎ出すころ。
同時に、警察にも通報がされたはず。
館を襲うために鬱陶しい警報装置を切った時点で、秒との戦いになっている。
館の人間を生かすなどという、面倒臭いことはしなかった。
『宝石商一家皆殺し!!世界最大のブルーサファイア奪われる!!!』が、メディアの連中が付けるタイトルか。
既に眼下には、警察車両の青い警告灯が目立ち始めた。
それにサイレンも五月蝿く鳴りだしている。
おかげで静まり返っていた深夜の街に、犬の遠吠えや、騒然とした雰囲気に何事かと、家々の明かりまでもが点きだす。
せっかく静寂の中に浮かんでいた幻想的な満月が、囂々たる状況に台無しだ。
もっともその原因を作ったのは誰あろう、この俺なのだが。
冴え冴えとした月明りの下、物情騒然となる
慌てふためく人影が、滑稽としかいいようがない
捕まえることの出来ない幻影を追いかける
追っ手がかかったからといって、そんなものに俺達の進路が阻まれるわけじゃない。
邪魔なものは排除すればよいだけのことなのだが、付録のような殺しは嫌いだった。
無駄働きのようで、建設的なものがない。
そのくせ満月の晩という理由だけで仕事をしてしまう。
ウソかマコトか、満月の晩は犯罪数が倍増するのだそうだ。
特に凶悪犯罪が多くなる。
何かしら月は人を興奮させるものがあるらしい。
同時に月は、ある種の波長で人を落ち着かせるとも言う。
俺の場合、満月が近づくと妙に冷めてゆく。
だから不安になり、自らテンションをあげようとしてしまう。
結果、理由をつけて血を見る仕事が多くなる。
そのくせ満月を見上げれば、壮観さに飲み込まれるという矛盾した現象が起こる。
しかも今夜はスーパームーン。
いつもより一回り大きい月……
「……そんなことって、お前にはないか?」
石を月に翳したまま、フィンクス訊ねていた。
「あるわけねぇだろうが。俺は団長ほどデリケートには出来ていないからな。月はいつ見たって、ただの月にしか見えねぇよ」
月どころか太陽にだって影響を受けなさそうな男に訊ねてしまったことに、俺は噴き出してしまう。
何を笑われたのか分からず、背後からは不愉快極まりないオーラが立ち上る。
わざわざ振り向くなんて、面倒なことはしない。
石を懐にしまい、眼下に蠢く生き物などには目もくれず、甍の海を走りだす。
余韻を残していた。
日光浴をするように、月光浴をしてみる。
青い月の明かりの中、おぼろげな自分の姿が見えて来る。
それは神秘性という不鮮明な言葉にも似ていた。
俺は全身で夜の太陽ともいえる月の光りを吸収する。
昼間の太陽では強すぎ火傷をしてしまう。
だから俺は闇に生きることにしたのだ。
俺は本能的に、己に相応しい光りを知っていた。
生まれ持ってのアウトローなのだと、笑うしかなかった。
End
2018/07/07 改稿
2009/07/19
どうもクロロとフィンクスが絡むと、哲学的になってくる。太陽よりも、月明かりが似合うクロロです。