眠れぬ夜……
カーテンのかかった窓の向こうから聞こえるのは、北風の鋭い音。
おかげで安普請なホームはミシミシと悲鳴をあげ、建物全体が小刻みに揺れる。
部屋の中央では燃え尽きた焚き火を囲み、昼間の労働に疲れた子供達が雑魚寝をしていた。
時折り寝言や鼾が聞こえてくるのはご愛嬌。
『……クロロ、眠れないの?』
深夜、蝋燭の揺らめく灯りの中で横になって本を読んでいると、毛布に頭まで包まっていたシャルナークが首を出し、可愛らしい声で訊ねてくる。
『ごめん。起しちゃったね。俺も、もう寝るからさ』
シャルナークは小さくこくりと頷くと、眠そうな目を擦りながら再び毛布に潜り込む。
肩口から冷気が入らぬようにしっかりと毛布を押さえてやれば、毛布の中から籠もった声が、
『おやすみ、クロロ』
と、優しく言ってくれる。
ふっと笑みを漏らしたが、この『おやすみ』が今生の別れの言葉になる場合もあることを知っていた。
読みかけの本を枕元に置くと、シャルナークの小さく丸まった姿を、俺は自分の毛布で更に包み抱いてやる。
そして目の前の蝋燭を吹き消し、自分も頭まで毛布にすっぽりと包まる。
こうすればシャルナークの体温が冷気に奪われることなく、俺自身もシャルナークの体温を分けて貰える。
うつらうつらしていると、燃え尽きたと思っていた焚き火の残り火が、パチッと爆ぜる音がした。
ホームと言えば何か温かな響きがあるが、それは名ばかりのもので、外気を薄い板一枚で隔てている空間にしか過ぎない。
冬になればシンシンとした冷気が壁の隙間から入り込み、外にいるのと大差がなかった。
かろうじて子供達のよりそう体温が、僅かに室温を上げる。
何しろ吐く息がホームの中でも白く、特に寒い日は飲料水用に溜めておいたバケツの雨水に薄氷が張るほど。
一応焚き火番はいるのだが、昼間の過酷な疲れから、どうしても明け方になると居眠りをしてしまう。
誰がそのことを責めることが出来るだろうか。
だから寝るまでは焚き火をどんどん燃し、少しでも暖をとってから寝床へと潜り込む。
冬のシーズン、何度かやってくる極寒の日。
寒さのあまり強い眠気をもよおすが、夜だというのにうかつに眠ることが出来ない。
否、夜だからこそ眠れないのだ。
体力のある者はいいが、ない者は寒さのために自然淘汰されてしまう。
翌朝、昨日まで生活を共にした仲間が骸になっていることがある。
包まった毛布は体温を失った身体を包んだまま棺へと変わる。
凍った大地に穴を掘ることも出来ず、永遠の褥を求め、近くの廃棄場へと皆で運ぶ。
天候が良ければ二日に一度、大型の廃棄物運搬用の飛行船団がやって来て、どんよりとした空から廃棄物を大量に落としていってくれる。
俺達は何もせずとも、廃棄物が骸を覆い隠してくれる。
棄てたのではない……
これが俺達に出来る精一杯の弔い。
誰の口から漏れたのか、
『ゴミ山に生まれたから、最期はゴミ山に埋められるんだね』
あまりにも切ない言葉に境遇という言葉を呪い、欲する力の原動力となった。
あれから何度凍てつく冬を越したのか。
今でこそ飢えることも、寒さに凍えることもなくなったが……
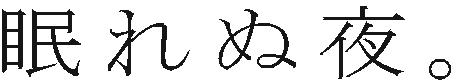
「……クロロ、まだ起きているの?」
女の眠そうな声が、俺の耳の中に籠もる。
「悪いな、起してしまって。……寝顔があまりにも可愛いかったから、見とれていた」
「…やだ、クロロったら」
女は『やだ』と言いつつもはにかみながら甘え、俺の胸に顔を摺り寄せるが、俺にしてみれば愛想で言った言葉に過ぎなかった。
それでも女の滑らかな黒い髪を無意識に撫ぜ、互いの体温を確認しあうように抱きしめてやる。
華奢な身体は小さく身じろいたが、疲れと安心感からか、再び深い眠りへと落ちてゆく。
女の名前を憶えてはいなかった。
行きずりで抱いた女。
たまたま目にとまり、好みであったことから声をかけた。
女を食事に誘いその後は、俺が泊まっている一流ホテルへと連れ込んだ。
最初から一晩限りの関係と決めていたから、名前など覚える気はなかった。
数日間の禁欲もあり、欲望をむき出しにして女を抱いた。
『……壊れる』と、女は何度も口にしたが、女もまた俺を貪り食おうとした。
その結果、精も根も尽き果て、泥のように眠る……
互いに満足を得て眠りについたはずだったが、俺は疲れとは逆に眠ることが出来ずにいた。
静まりかえった部屋の中に聞こえるのは、鋭いビル風の音。
高層ビルの間を抜ける都市特有の音に眠れない。
本当は音など聞こえてはいなかった。
高級ホテルの防音設備は完璧。
だが北から吹き抜けてくる風が、大きな分厚い窓ガラスにぶつかり、行き場を失ったことに抗議するかのように、ガラスを震わす。
それが音としてではなく、感覚として皮膚に伝わってくるのだ。
部屋の中は裸でいられほどの暖かさなのに、冷え冷えとした圧覚に囚われてゆく。
女が目覚める前にチェックアウトするつもりだった。
過去の経験から言えば下手に目覚めを共にすると、勘違いを起した女に憑りつかれることが多く、うざいこと極まりなかったから。
だが今はそれを置いても人肌を求めていた。
体温という温もり。
記憶に残る冷たい毛布の塊に、絶望と虚無感に襲われた子供時代。
厳寒という名前の死神に魅入られた、仲間の名前を忘れることが出来ずにいた。
力を手に入れた今でも消えることのない記憶。
むしろ残酷な記憶は鮮明さを増して行く。
本当に求めたものは何だったのか。
縋るように抱きしめた体温の温かさに安堵する。
眠れぬ夜……
寒さの中を生き延びたことへの喜びと、助けることの出来なかった小さな命への罪の意識。
身を切られるような心の痛みに、風の音が死者の咆哮のように聞こえる。
いつまでも囚われ、忘れることの出来ない記憶に心を抉られるようだ。
END
2018/11/11 改稿
2009/11/13