初冬、刈り取られた広大な穀倉地帯が、モノクロームに染まる。
ヘッドライトに照らし出された街道を、黒いセダンが走り抜ける。
舗装されているとはいえ田舎道、荒れた路面の悪さに時折り車が跳ねる。
車には、仕事を終えた二人の男が乗っていた。
男達の生業は盗賊。
それもA級賞金首という冠までついた大悪党。
後部座席には仕事の成果である、年代ものの革装丁がなされた古書が一冊、無造作に投げ込まれていた。
この一冊の本を得るために、緻密な計画が練られたのだが、肩すかしのような偶然が重なり、あっさりと目的を果たしてしまう。
仕事の醍醐味を失い、あれほど欲しかったはずの古書に対する熱も冷めてしまう。
おかげで仕事の後の満足感がなかった。
車のラジオから微かに聞こえて来るのは、地元のFM局が流す軽音楽……
ハンドルを握るのは、額に包帯を巻いた黒髪の男。
助手席ではシートの背を半分ほど倒し、ダッシュボードの上に足を投げ出す金髪の青年。
この数ヶ月、金髪青年は連続する黒髪の男の仕事に翻弄されていた。
仕事をするための情報集めに、実務をするための計画。
それに実行という流れだが、成果があってないような今回の仕事に、溜まっていた疲れがどっと出てしまう。
本来なら金髪青年が運転をするところだが、青年の様子を見て黒髪の男が運転を代わることにした。
まどろみながら、変化に乏しい景色を窓越しに追っていた。
一色で描かれた夜の何もない耕地に、点々とある雑木林を走り抜ける。
既に葉を落とし、枝だけとなった木々を、待宵月が影絵のようにシルエットを浮き上がらせる。
半分夢の世界に入り込んでいた助手席の青年は、ふとした光景に意識が覚醒されてしまう。
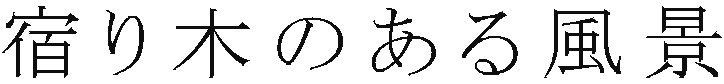
「……あのさ、さっきから気になっているんだけど」
「何だ。寝るんじゃなかったのか?」
「寝るつもりだったけど、外の景色が気になってさ」
「景色?」
「うん。ほら、枝だけになった木の上に、時々丸い塊りがあるけど、鳥の巣にしては不自然だし……」
助手席の青年が倒れていたシートを起こしながら、
「ほら、今も木の上にあった。いったい、あれは何なんだろう?」
シートから身を乗り出し、指差す金髪の青年。
ハンドルを握る黒髪の男は、指し示す雑木林の上の方に目をやる。
ほぼ満月に近い月明かりが逆光となり、葉の落ちた枝が重なり合うのが見えた。
そこに黒々と、一抱えもある葉の繁る塊がある。
「……ああ、あれか。あれは宿り木だ」
「やどりぎ?」
助手席の青年は黒髪の男に顔を向け、鸚鵡返しに訊き返す。
するとハンドルを握る黒髪の男が話し出す。
「そう、宿り木。この地方では、イナリーとも呼ばれている。オークというブナ科の木に寄生する植物だ。クリスマスにモミの木のリースを飾るように、玄関先に枝を飾る風習がこの辺りにはある。そのまま枝だけを飾ったり、リボンやーオーナメントで飾る場合もあるようだ。宿り木は特定の樹木に寄生する植物で、場合いによっては寄生する宿り主の栄養分を吸い取り枯らすこともある。そこが共に生きる共生植物とは大きく違う。世界中のいたる所で見ることができるが、種類も多く、形も植生も様々だ。繁殖力はそれほど強くないが、宿り主を駆逐してしまうこともあることから、生命力のシンボルとされることが多い。重病人のいる家では病人の寝室のベットの上に飾り、病気の回復を祈る風習があるとか。念願叶って回復すると、感謝の意味をこめて寝室の入口に飾り、快気祝いをするそうだ」
朗々とした講釈に聞き入った金髪青年は、合点がいったのか、こくりと頷きながら、
「以前、軒先に飾られた丸い枝の塊りを見たことがあるけど、あれは宿り木だったんだね。それにそんな深い意味があったとは」
納得する金髪青年を横目に、黒髪の男の講釈は続く。
「地域によってはクリスマスに関係なく、魔除けの意味をこめ、一年中飾られている地方もあるそうだ。宗教というより、呪術的な意味が深いみたいだな。昔の人間は宿り木の生命力に、畏怖と神秘性を感じたのだろ。不思議なことに宿り木は、寄生する樹木から離しても、一年中青々としているんだ。つまり宿り木は寄生しなくても生きていけるが、より強く育つために寄生するという植生で、更なる進化の可能性を増やしたということらしい。ただし繁殖するためには、寄生樹木が必要なのだが」
黒髪の男が一気に話し終えると、金髪青年が感慨深げな顔になる。
「なんだか宿り木って、俺達みたいだ」
「俺達……幻影旅団という意味か?」
「そう。正確には蜘蛛の手足。頭である団長を除いて、という意味だけどね」
「……俺を除いて?」
「そう。クロロを除いての話し」
「俺を除いてって、ずいぶんと薄情な言い草だな。つまり俺は、お前達の仲間ではないということか?」
金髪青年の予想しなかった話しのふりに、黒髪の男は訝しく思いながらも興味を示す。
蜘蛛とも呼ばれる幻影旅団は13人のメンバーから構成される。
互いを仲間、頭、手足と呼ぶが、そこには最初から束縛しあう上下関係はなく、必要な時だけ関係を濃縮させることで、互いの信頼を高めるという、彼らが長い時間をかけて独自に作り出した人間関係がある。
特に幻影旅団設立当初のメンバーは、流星街育ちの同じ釜の飯を食った関係から、特に精神的な繋がりが強い。
その中で生かされるべきは蜘蛛という掟を作り、時と場合によっては手足を生かすため、頭でさえも切り落とす覚悟でいる。
こうして何者にも縛られない盗賊集団、幻影旅団が生まれたのだ。
ドライだがホットな関係を楽しむように、黒髪の男の口元が上がるのを、助手席の金髪青年は見逃さなかった。
「団長は……否、クロロは、仲間と言うのには当てはまらないよ。なぜなら団長あっての蜘蛛。クロロ=ルシルフルあっての俺達だからね。クロロの存在なくして、非力な子共だった俺達が流星街で生き抜くことは不可能だった。たとえ生き延びたところで、今のような生活はありえなかったと思うんだ。クロロの知恵と行動力があれば、クロロがわざわざ俺達のリーダをやらなくても、もっといい選択肢があったはず。それなのに、俺達と運命を共にしてくれた。そして俺達に相応しい道を切り開いてくれたんだ。大人になった今、俺達は独立して生きて行けるはずなのに、俺達はまだクロロに寄生している」
金髪青年はシビアな話しであるにも係わらず、へらっと話した。
対して黒髪の男も笑いを堪え、軽い口調で返す。
「俺に対し、泣けてくるほど高い評価だな。だが生憎と、俺がお前達と付き合ってきたのは、そんな情け深い話しじゃない。だいたいお前達が俺の人生で、足枷になったことも、縛りをかけてきたこともない。むしろ俺の人生に、彩りを加えてくれているんだ。だからこれからも、限られた人生を楽しむための相棒であって欲しいと願うんだが。そういう意味では寄生ではなく、共生だな」
「……共生、ね。クロロがそう言うなら、それでもいいけどさ……俺、疲れているから寝るよ」
助手席の金髪青年は眠そうな声で言うと、シートを最大限に倒し、目を閉じるとすぐに寝息をたて始める。
黒髪の男はちらりと助手席を見て、ふっと笑いを漏らす。
そしてすぐに視線を前方に戻した。
どこまでも続く道
途中、小枝が分れるように幾すじもの道はあったけど……
走る車の正面に、ゆっくりと闇を溶かすような明るさが、遥かなる穀倉地帯の地平線に現れる
シルエットだった雑木林が、徐々に色味を帯びてくる
葉を落とし、枝を剥きだしにした樹木に付着した夜露が氷となって、白い輝きを放つ
高く伸びた枝の先端近くには、いくつもの青々と茂る塊りが存在を主張する
それはまるで、生命力を示すかのように……
End
2017/12/31 改稿
2011/12/19 加筆・修正
2010/12/24 加筆・修正
2009/12/14
2009年に初めて中欧旅行に行き、移動の車中で見た田舎の風景が印象に残り、車中で下書きをして、日本に帰ってきてから仕上げたが、そのまま放置。2010年2011年の12月にも中欧へ再度旅行し、帰国する度に手直しをして、やっと日の目を見ることに。久々の三人称展開。仕事帰り、車中のクロロとシャルナークの何気ない会話。