Syarnorke 45
「あ~ん、シャル。」
喉を撫でるような甘い声を耳にしながら目を瞑り、俺は柔らかい笑みを浮かべてゆっくりと口を開ける。
口の中に優しく人差し指で押し込まれた丸い物体は……異状なまでに甘かった。
……甘過ぎる。
当然だよね、チョコレートなんだから。
中身はどろりとした甘いリキュールではなく、甘さを抑えたラムトリフだが、それでもかなり甘い……
俺が甘いものをそれほど好きではないってことを、話してはいなかったけ?
できればビターチョコレートにして欲しかった。
ガラステーブルの上に広げられたチョコレートの入っていた箱と包装紙を、薄く目を開けて見ていた。
黒をベースにした紙に、赤と金色で店の名前がセンスよく印刷されている。
せめてもの救いは手作りではなく、高級チョコレート店のチョコレートだったということ。
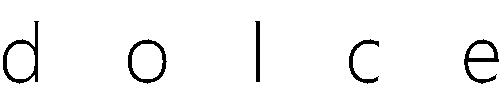
入れる時よりも更にゆっくりと引き抜かれる指の感触を、敏感になった唇と舌が味わっていた。
しかも引き抜く瞬間唇を窄めて唇で舐めるように指を押しだせば、俺の鼻先で小さな吐息が漏れる。
目を開けてくすりと笑えば可愛らしい顔が金色の髪を揺らし、感じてしまったことへの恥ずかしさに俯いてしまう。
いつも愛の告白は本能の赴くままにしている。
愛を求める女の子には十分な寵みは与えているつもりだ。
もっとも誰かれに与える気はないけれど。
あくまでも俺のお眼鏡にかなった娘だけに限定される。
だからわざわざバレンタインデーなんて、まどろっこしいイベントなんかしてくれる必要はないんだ。
甘い言葉を囁き疑似恋愛をして、後はお互いにベットの中で気持ちよくなればいい。
ソファーに浅く腰掛け、太腿の上に深く彼女を跨らせていた。
腕を奢な腰に回し、たまに脇腹をくすぐるように撫ぜてやる。
するとくすぐったいのと感じるのとで、無意識に俺の太腿の上で彼女は腰を揺らす。
その仕草がたまらなく可愛い。
彼女とは最近付き合い始めたばかりで、ヨルビアン大陸系の女の子。
既に何度か肌を合わせたけれど、慣れることがなくていつも初々しい。
今だって恥ずかしそうにもじもじとしているけれど、それがどんなに俺のことを煽っているのか分かっているだろうか。
フレアスカートがめくれあがり、俺の腰を挟んだ彼女の折り曲げた太腿が剥き出しになっている。
スカートに隠れた足の付け根に手を差し入れゆっくりと撫ぜ上げれば、『……あっ』 と小さく歓喜の悲鳴にも似た声をあげる。
このじゃれている時間がけっこう楽しいんだ。
それなのに彼女は突然押し黙り、こちらが何事かと心配していると、やっと口を開いた。
「ごめんね、シャル」
「どうしたの急に?」
すまなさそうな顔で、俺の顔を上目使いで見つめてくる。
「……市販のチョコレートをプレゼントするなんて、愛情が薄いと思われてもしょうがないよね。私、お菓子作り下手だし……でも来年は、絶対に上手くなって手作りでプレゼントするから」
へっ!そんなこと。
悪いけど、むしろ手作りでなくて感謝しているくらいだ。
ど素人が作ったものよりも、プロが材料を吟味して作った方が美味いに決まっている。
しかも、来年のバレンタイデーまで、付き合っているなんてありえない。
半年先だって保障の限りじゃない。
心の中で思ったことはおくびにも出さず、愛情いっぱいの笑顔を作った。
「有難う。嬉しいよ。それじゃあ来年は、期待して待っているから」
そう言いながら顎を取り、ふっくらとした唇に口付けを落とす。
……君は知らないの?
確か信頼できる男性雑誌のアンケート調査によれば、男が彼女からプレゼントして欲しい物の第一位は手作りの品。
そして貰って一番嬉しくない品も手作りの品だってことを。
しかもポイント的には、後者が前者をはるかに超えているという事実。
男って、女が思っているほど手作りには飢えていないんだ。
むしろ愛情の押し売りをされているようで負担になってくる。
私はこれほど彼方を愛しているのよって、無言で重圧をかけられているみたいだ。
たとえばこれがセーターやマフラだったら、一目一目に愛情という怨念をこめて編み上げているようで怖い。
だいたい別れた後どうするんだって!?
一目で手編みだと分かる品を、いつ次の新しい彼女がくるとも分からない部屋に置いておけると思うの?
重すぎて記念にとっておく気にもなれない。
ゴミ箱に放り込まれるのが関の山。
だから貰っても、最初から印象に残らないようなものの方が有難い。
どうせ時期に別れてしまうのだから……
そう考えながらも、彼女と深い口付けを交わしていた。
ピンポ~ン
ピンポ~ンって……誰だよ!
かなり雰囲気が盛り上がっていたところに、水を差す無粋な来訪者。
どうせ俺の隠れ家にやってくるなんて、飛び込みのセールスくらい。
何しろこの場所はクロロにだって教えていないんだから。
ともかく無視するのが一番と、知らん顔を決めたのだが……
ピンポ~ン、ピンポ~ンって、何度も何度もしつこく鳴らされる。
それは家の中に誰かが居ることを確信して鳴らしているようだった。
さすがの俺も、しつこい謎の来訪者にぶち切れ寸前!!
腕の中の彼女も困って苦笑いをする。
「ごめん。ちょっと待っててくれる」
太腿の上に乗せていた彼女をソファーに座り直させる。
怒りを露わにしてソファーから立ち上がり、大股で歩いて壁に掛けられたテレビドアホンのスイッチを乱暴に押す。
大型5.2インチの液晶ディスプレイには見知らぬ若い女が二人映り、こちらを覗き込んでいる。
何なんだ、この女達は!新手の新興宗教の勧誘か!?
じっくりと二人組の女の顔を観察すれば、手前の女の背に隠れるように立っている女には、見覚えがあった。
「はい。何でしょうか?」
俺は感情をこめずに冷たく言い放つ。
すると手前にいた女が、
『すいません。シャルナークさんですよね。わたし、メイの親友でナシカと言います』
ナシカと名乗る女は、後ろにいるメイという女を前へと引っ張り出してくる。
あぁ……知っているよ。
俺がたまに行くレストランで働いている女の子だ。
俺のお気に入りの席を担当している娘。
オーダー以外に、たまに世間話しをする程度の関係。
気さくなせいか、店の客にはけっこう人気があるようだった。
「それで何か用?悪いけど、今来客中で、君達に構っている暇はないんだけど」
言葉の中に目一杯の不愉快さを滲ませてやった。
だがナシカと名乗る女は動じることなく、
『メイのことは知っていますよね?メイがあなたに一目惚れしちゃって。今日はバレンタインデーだから、是非チョコレートを受け取って欲しくて伺ったんですけど』
ナシカはメイの肩に手を置き、ドアカメラに良く映るように前へと押し出す。
その手にはしっかりとプレゼント用に包装された小さな箱が握りしめられている。
こういう場合、本人よりも親友と名乗る女の方が性質が悪い。
応援のあまり、本人以上になりふりを構わないから。
「今も言ったように来客中なんだ。このまま帰ってくれる」
とたんに不安げな顔をしていたメイが泣き出しそうになる。
横にいたナシカがメイの肩を支え興奮気味に言った。
『すぐに帰ります。だからメイの気持ちを受け取ってやって下さい。メイは忙しい仕事の合間を縫って徹夜して、あなたのために手作りでチョコレートを作ったんです』
だから何だっていうんだ。
あなたのためにって、俺はそんなことを頼んだ覚えはない。
だいたい秘密にしていた俺の隠れ家を探し出すこと自体、ストーカー行為だろうが!
それについては何も感じないわけ?
もっとも彼女達に後をつけられていたとしたら、それはそれで間抜けな話しだ。
おかげで自分にも彼女達にもムカついた。
カメラの前で仁王立ちするナシカに容赦なく引導を渡す。
「俺は付き合っている彼女がいる時は、別の女の子からチョコレートは受け取らないことにしているんだ」
『……』
「君達だって、自分の彼氏が他の女の子から貰ったチョコレートを食べていたら気分がいいかい?俺は彼女に辛い思いをさせたくないから、受け取るわけにはいかないんだ」
俺が言い終わると同時に、ディスプレイには屈みこみ嗚咽を漏らすメイの姿があった。
そんな姿を見たからといって情けをかける気はない。
だいたい気もないのに、笑顔でチョコレートを受け取る方が残酷だろうが。
不必要に気をもたせないことの方が、一番の思いやりのはず。
親友の取り乱した姿にナシカも屈みこみ、必死にメイを慰めていた。
そしてしばらくすると立ち上がり、
『そうですね。シャルナークさんのおっしゃるとおりですよね。突然おじゃまして本当に申し訳ありませんでした。私達、これで失礼させていただきます』
そう気丈に言うなり、肩を落とした二人はディスプレイから消えてくれた。
そして俺もドアホンのスイッチをオフにした。
何もここまで強く言う必要はなかったか……
いつものとおり、シャルスマイルで受け取っておけばよかったのか……
そんなこと、許せるはずがなかった。
何故って……
振り向けば君がそこに居て、不安そうな顔で俺を見ていた。
心配しないで……
今愛しているのは君だけだから。
そう……今は一番好きな彼女だから、今だけは悲しませるようなことはしないから。
思わず彼女抱きよせ、甘い甘いチョコレート味のキスをする。
End
2017/02/01 改稿
2009/03/15 加筆・修正
2009/02/12
![]() Back
Back
男性が手作りをさほど喜ばないというアンケート調査を見た時、やっぱり感が強かった。