かわいい顔をして、やることがえげつない。
そう……汚いとか悪質と言うより、ルキアのやることはえげつないんだ。
俺はそんな彼女のえげつなさを愛している。
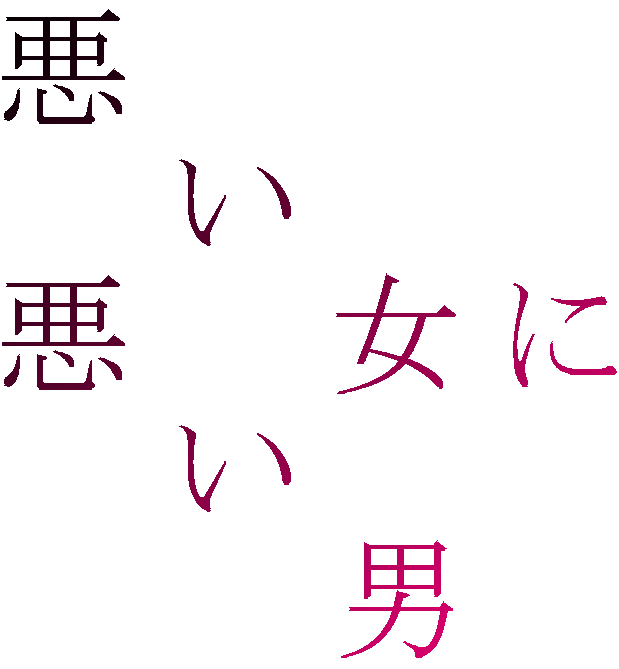
【えげつない】を辞書で引けば、言い方が露骨、無遠慮で節度を超えるさま。
または下種で下品なさまとあるが、ルキアは上流家庭に生まれ上品で優雅だが、狙いを定めた獲物にはえげつない手段を使う。
欲しいモノはどんなことをしても手に入れる。
悪びれることなく、ひたすら目的に向って突き進む。
そこにあるのは捕食者の顔。
何不自由のないお嬢様のくせに、どうしたらこんなに貪欲になれるのか。
俺はそんなルキアに翻弄される。
「……何もあそこまで酷いことをしなくても」
「だって、そんなこと言ってもしょうがないじゃない。ライバルは早めに叩いておかないとね。出る杭は打つより、出る前に折っておいた方が後々面倒にならなくていいと思うの」
打てば再び出てくるかもしれない杭。
ならば根元から折ってしまった方が、確実に相手を葬り去れるということか。
口調はいつもどおり穏やかで、鈴を転がすような声。
香り高い紅茶が注がれた白い磁器のティーカップを持つ姿が優美。
惚れた弱みというか、美しい仕種に見惚れてしまう。
さらりと出てきた残酷な言葉までも、魅力的に聞こえてくるから不思議だ。
柔らかい笑みを浮かべ、形のよいピンク色の唇がティーカップに寄せられる。
「私のシャルに言い寄ったんだから当然の報いよ。それに彼女達も、好きな人に殺されるなら本望でしょ」
『私のシャル……』俺を喜ばせる一言に、俺はルキアにメロメロだ。
それで、言い寄られたのか言い寄ったのか。
確かに女の子から言い寄られる場合もあるけれど、大抵の場合は俺の方からちょっかいをかける。
もっとも粉をかけても拒否しなさそうな、俺好みの女の子を最初からチョイスしてはいるけれど。
俺はルキアに惚れているけれど、心と肉体は別物で、特に俺の下半身に人格はない。
ルキアという御馳走とは別に、食指が他に動くことがある。
世間一般に言う浮気というやつだが、ほんとうに浮ついた気持ち。
狙いを付けた女の子を口説きベッドに連れ込んでも、最初は目新しい食べ物に感動を覚えていたはずが、数回口にすると飽きがくる。
俺にはルキアという、もっと美味しい食べ物があったことを思い出す。
身体全体が、俺にとって一番美味しい食べ物が何であるかを教えてくれる。
結果、もっとも大切な女の子が誰なのかを再認識させられることに。
所詮浮気は浮気で、しょうこりもなく同じことは繰り返される。
浮気相手に求めるものは、足の付け根で行う気持ちいい行為で、ルキアに求めるものはそれだけじゃない。
それにしても何て嫉妬深いんだ。
俺と関係を持った女の子を、俺自身に殺させるなんて。
でも、どうやって?
俺の操作系の能力同様に、ルキアには天才的な催眠術の能力がある。
形は違えど、俺は大好きな女の子にどこかで操作されているらしい。
いったいいつの間に催眠術にかけられたのだろう。
もっともルキアの声を聞いているだけで心地よいのだから、かけられる隙はいくらでもあったはず。
いまさら『いつ?』と訊いてもしょうがない。
問題なのは殺すという暗示。
俺にはたくさんの殺人経験があって免疫があるけれど、普通の人間には殺人というのはとても高いハードルとなる。
たとえ『殺せ』と命令されても理性が邪魔をする。
俺が『携帯する他人の運命』で、気軽に『殺せ』と携帯に書き込むのとはわけが違う。
念能力と催眠術の操作の大きな違いは、念能力で操作する命令には逆らう術がないけれど、催眠術はかけられる人間の意思やモラル、性格によって受け付けない場合が多々あるということ。
だから『殺せ』という命令は意識下で、拒絶の対象となって実行されにくい。
催眠術で人を殺すなんて、小説とドラマの中だけでの話し。
それに生きるための本能的な部分にも催眠術は効かない。
たとえば『自殺しろ』と催眠術をかけたとしても、本能が受け付けない
ルキアは最初、俺に浮気を防止するための催眠術をかけたらしいが、俺の浮気は本能的なものらしく、防止することは出来なかった。
そこで業を煮やしたルキアは手っ取り早く、浮気相手を俺の手で葬り去ることにしたのだ。
モラルという言葉は遠い昔に捨てていた。
失ったハードルのおかげで、ついさっきまでベッドを共にし、愛していると言ってくれた女の子でも躊躇せず殺せる。
だから俺に催眠術なんか必要ないのに。
ルキアが一言、浮気相手は情事の後に処理して頂戴と命令してくれればそれで済む。
「教えてよ、ルキア。いったい俺にどんな催眠術をかけたのさ」
少し拗ねたように言えば、くすりと笑ったルキアは、
「ひ・み・つ」
唇に人差し指を宛がい、一文字一文字を区切って言った。
あァ~~~悔しい。
俺は完全にルキアの掌の中で泳がされている。
木乃伊取りが木乃伊になった……
なにしろ街で見かけたルキアの可愛らしさに一目惚れをして、口説き落として一夜を楽しもうとした。
なんとか甘言を弄して付き合い始めたが、すぐに催眠術をかけられ、素性を偽って近づいたのがばれてしまう。
なのに……
極悪非道のA級賞金首のお尋ね者の俺を、恐れることなく愛してくれている。
人使いの荒い誰かさんの愚痴を、『ウン、ウン』と頷きながらいくらでも聞いてくれことが嬉しい。
仕事が行き詰った時は優しく労い、時として素晴らしいインスピレーションを与えてくれる時もある。
情事の後、俺の背中の蜘蛛を愛おしそうに撫ぜる仕草に癒される。
爽やか腹黒……俺の方も隠すものがなく、俺にとってルキアは素を晒して付き合える唯一の女の子。
ルキアにとって俺は、優しさと残虐性を見せられる初めての相手で、気兼ねなく付き合える相手らしい。
互いに互いがよき理解者となり、一夜のはずが三年以上続く関係となり、これからも二人の関係は続いてゆく。
ベッドのヘッドボードを背にし、足はマットレスに投げ出していた。
シャルが淹れてくれた朝の紅茶を楽しみながら、たわいもない会話で時を過ごす。
飲み終わったティーカップをトレイに置けば、掛け布団の上にセットされていたベッドトレイをシャルが片付けてくれる。
お嬢様である私にとってメイドがやってくれる日常的なことであっても、大好きなシャルがやってくれるとなると話しが違う。
シャルの至れり尽くせりの行動に、私はとても幸せだ。
昨夜の行為で乱れた私の金色の髪を、シャルは丁寧にブラシで梳いてくれる。
そして朝日の中に輝く髪を一房とって口付ける。
「ルキア、愛してる」
「私も愛してるは、シャル」
こんな言葉を素直に言える相手は、人生においてたった一人だけだろう。
なのにこの男ときたら、生来の女たらし。
女の子と付き合うのが本能だというのなら、防止策の催眠術は役にたたない。
ならば攻撃は最大の防御なり。
『あなたの一番愛すべき女性の命を、あなたと今寝た女が嫉妬に狂い狙っています』と、催眠術をかけた。
『殺せ』なんて、一言も命令しなかった。
シャルが女の子達を情事の後に殺したのは、最愛の私を守ろうとしただけ。
第三者から見れば、さぞかし私のやっていることはえげつない行為かもしれない。
だけどこの私を守るという行為が、最高のお姫様気分に私を押し上げてくれる。
屈折した愛情……私達は浮気と嫉妬で愛を確かめ合っているのだから。
End
2017/03/21 改稿
2011/04/07