Syarnorke 98
たまたま立ち寄った城郭のそびえる街。
第一日曜日、古風な市庁舎前の広場は蚤の市で賑わう。
何となく区画割りされた路上には、プロとアマチュアが肩を並べて店を出す。
時によってはプロが開く店よりも、アマチュアの方が面白い品や掘り出し物があったりする。
まさに我楽多の中のお宝探し。
だから客は冷やかし半分、本気半分で店を回る。
宝探しの勝負は本物を見抜く目だが、大半の人間に本物を見抜く眼力なんてありはしない。
そもそも本物を知らないのだから、お宝を見付け出すことなんてほぼ不可能。
店を覘く連中の会話に耳を澄ませば、口だけはいっぱしの鑑定家。
ど素人のうんちくと評価に、思わず皮肉な笑いがこみ上げる。
せいぜい偶然に頼るか、フェイクかジャンク物と知ったうえ、気に入った物を日用品として手に入れるのが身分相応というもの。
そのオルゴールを見付けたのは偶合の産物。
まさかこんなところで出くわすとは。
俺の場合冷やかし半分ではなく、完全に冷やかしだった。
並べられた我楽多を流すように見ていたのだが……
盗賊家業をやっていると嫌でも目が肥えてくる。
何しろ襲うのは美術館や金持ちの館ときているから、自然と知識は身に付いてくるし、本物と接することが多くなるわけで、必然的にお宝を見抜く観察力も育ってくる。
そのうえ我儘な誰かさんと付き合っていると、否応なく博学になってしまう。
だから何気なく覘いた廃品、否!我楽多の中で光る品に、目が吸い寄せられてしまう。
年月を経て多少の汚れや煤けた感じはあるけれど……
立ち止まった体勢のまま膝を折る。
商品を傷付けぬように地面に引かれた厚手のビニールマット。
その上には溢れんばかりの品。
一目で使用目的が分かる品もあれば、一体何に使うのか不明なものまで雑多に置かれている。
特に年代や製品別に分けることもなく、店主の雑な性格が浮き彫りになっていた。
美しい楡の玉杢に、金線や銀線を幾重にも象嵌をした繊細な小箱に手を伸ばす。
さり気なく手に取り、何気なく見ているかのように見せることが重要。
少しでも商品に対する熱があると思われたら、いいカモにされてしまう。
逸る気持ちを抑え、手にした品を確認する。
これって、俺とクロロが数年越しで探しているオルゴールの一つだ!
俺は表情を変えず、心の中でにやりと笑う。
そしてごく自然に言った。
「ねぇ、この箱、開けてもいいかな?」
商品の向こうで簡易な椅子に腰掛け、暇そうに週刊誌を広げていた女店主は顔だけをこちらに向け、
「どうぞ。その箱はオルゴールですけど、長年うちの倉庫に放置されていた品で、壊れていて鳴りませんよ。中身にオルゴールのムーブメントが入っているので、箱としては使えないので、飾りとして楽しむことしか出来ませんから」
三十代後半であろう女はそっけなく答えると、読んでいた週刊誌に再び視線を落とす。
手に取ったオルゴールは掌に乗る大きさだが、見た目より重い。
確かに蓋を開けても、オルゴールとして機能を果たさない。
それでもムーブメントには塵一つ付いておらず、真鍮の美しい輝きがある。
目の高さに翳し、四方くまなく仔細に眺める。
どこにも製作者を示すサインはないけれど、この品自体が作り手を雄弁に語っていた。
このオルゴールを作ったのは、三百年前の時計技師アルフォンス=ラメック。
パドキア共和国がパドキア王国と呼ばれていたころの、王家に仕える天才時計技師。
当時の時計技師はその手先の器用さから、カラクリ人形やオルゴールなどの細かな細工物も作っていた。
このオルゴールも彼が生涯で作ったとされる、二十一個のオルゴールの一つ。
なぜ二十一個かといえば、王が離宮に抱えた愛人の数だと言われている。
早い話し、愛人のためにプレゼントされた品なのだ。
もっともプレゼントといっても、このオルゴール一つで一生を安泰に暮せる価値がある。
王が亡き後、愛人達が困らぬように与えた、一括払いの年金のようなもの。
二十一人という愛人が、王と呼ばれる人間の生涯で少ないのか多いのか分からない。
英雄色を好むという言葉もあるけれど、愛人達の生涯を保障した強者はそういない。
男の鏡とも言える行いに、尊敬の溜息と、気苦労の多さに目眩すら感じる。
平穏無事に一生を終えることの出来た愛人の数は二十一人。
そしてその子供の数は八十二人。
ちなみに正妻である王妃との間に出来た子供の数は八人。
……避妊などという観念のない絶倫な王様に頭が下がる。
子沢山の王妃は、王が自分の地位を脅かす側室を持つことを許さず、かろうじて愛人を離宮に囲うという形でその存在を認めた。
当時、もっとも最盛を極めたというパドキア王国。
貴族の娘を中心に、王のお気に入りの女達。
何不自由のない贅沢な生活。
とどのつまり、全ては経済力がものを言うのだ。
この露店の女主だって、もしかしたら王の寵愛を受けた愛人の子孫かもしれない。
現在行方が分かっているオルゴールは十二個で、四個はクロロが手に入れ、後はパドキア共和国に住むマダム・ガリッシュがコレクションしている。
クロロはマダム・ガリッシュが十個ほど集めたら、ちょうだいしようと目論んでいる。
まるでハイエナのような仕事だけど、もっとも効率がいい。
だから俺は定期的にマダムの行動を見張っている。
二週間後にあるヨークシンの地下競売に、お目当ての品が三点出品される予定。
当然マダムも参加するわけで、金に糸目を付けずに落札するだろう。
これでマダムのオルゴールは十一個となり、計画どおりクロロの手にオルゴールは転がり込むという寸法だ。
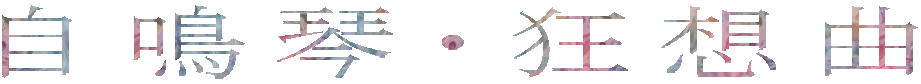
実にあっさりした交渉だった。
地下競売なら一個十二億ジェニーは下らない。
それが価値の分からない売主は、心臓部であるムーブメントが壊れているからと、たったの四千ジェニーで手放した。
新聞紙に包み、ビニール袋に放り込まれたオルゴールを手にぶら下げ、仮宿であるホテルへと戻る。
俺はベッドに腰を下ろし、オルゴールを手にした。
いつになく昂ぶっている。
それもそのはず、確率は極めて低いけど……
手にした小箱はオルゴールである以上に重たいような気がする。
もしも俺の勘が当たっていれば……
箱を飾る象嵌に目を凝らす。
全神経を集中させ、緻密な細工を探る。
紙の厚さにも満たない、僅かに開いた木部と金属の境を見付ける。
このオルゴールが制作された時点なら、こんな隙間はなかったはず。
三百年の時が木部の乾燥を生じさせた。
俺はにやりと笑いながら、指先は立体パズルを解くかのごとく、箱の表面に施された仕掛けを解除してゆく。
箱を構成する薄い側板を、右へ左へ、上へ下へ。
仕掛けは七回ほど動かすことで解き放たれ、取り外された底板から転がり落ちたのは、二百カラット以上はあるであろう高品質なダイヤモンド。
しかも見事なカットがなされている。
権力に物を言わせ、弱国や植民地から貢がせた宝。
俺はベッドカバーの上に落ちたダイヤモンドを拾い、窓から差し込む日の光りに翳す。
三百年ぶりに日の目を見た宝石が、煌びやかに輝く。
象嵌された小箱のオルゴールだけでも価値があるというのに、王は更なる保険を付けていたのだ。
秘密の場所に隠された宝石を、どれだけの愛人が気付き、手にしたことか。
愛する女と子供達のために用意されたお宝。
それとも王は、本当のお宝である宝石をオルゴールに隠したことを、愛人達に教えていたのだろうか。
男盛りで病に没した王の亡き後、想像を絶する浪費家の王妃と子供達が国を傾け、一斉蜂起した民衆が革命を起こす。
断頭台に消えた直系の血筋……
このオルゴールの持ち主である愛人は、亡き王を想い、思い出の小箱を愛しみ手放すことはなかった。
もちろん宝石が隠されていることは知っていたが、金に換えようとは露にも考えはしない。
全ては愛する王を想う気持ちから。
二人の思い出が詰まったオルゴール……
なんてね……都合よく想像するのは、誰かさんの歴史に対する浪漫が伝染したのか。
そうでも思わなければ、本当の愛に出会うことが出来そうにもないから。
♪♪♪♪♪……♪♪…♪♪♪♪♪♪……♪♪♪……
ベッドの上に置いたオルゴールが、突然音楽を奏で始める。
壊れていたはずなのに……
俺が底板をはずしたのがきっかけとなり、ムーブメントが刺激されて動き始めたのか?
王と愛人が愛した曲。
二十一個のオルゴール全てが違う曲を奏でるという。
愛人達をイメージするオリジナル曲は、王の肝いりで作られた。
めくるめく、オルゴール・ラプソディー。
古の愛が今蘇る。
耳を傾ければ王と優美で可愛らしい女性が、ふざけながら鬼ごっこをしているのが見えて来るようだ。
離宮の広い庭、楽しそうに絡み合う二人……
そこには権威も権力もなく、ただ愛し合う男と女がいるのみ。
やっぱり俺って、ロマンチストかもしれない。
手にしていたダイヤモンドを、秘密の隠し場所にそっと戻す。
それから一ヵ月後、クロロはマダム・ガリッシュのコレクション十一個を手に入れた。
この勢いで、全てのオルゴールを我が物にしようと鼻息も荒いクロロだったが、それは無理な話し。
なぜって、少なくとも一つは俺の隠れ家の棚に飾ってあるから。
この部屋に帰ると、まずはオルゴールの蓋を開く。
そしてベッドに寝転び、穏やかな曲に癒される。
クロロには当然だが、誰にも話すことのない俺だけの秘密♪
END
2017/06/26 改稿
2011/09/20
![]() Back
Back